
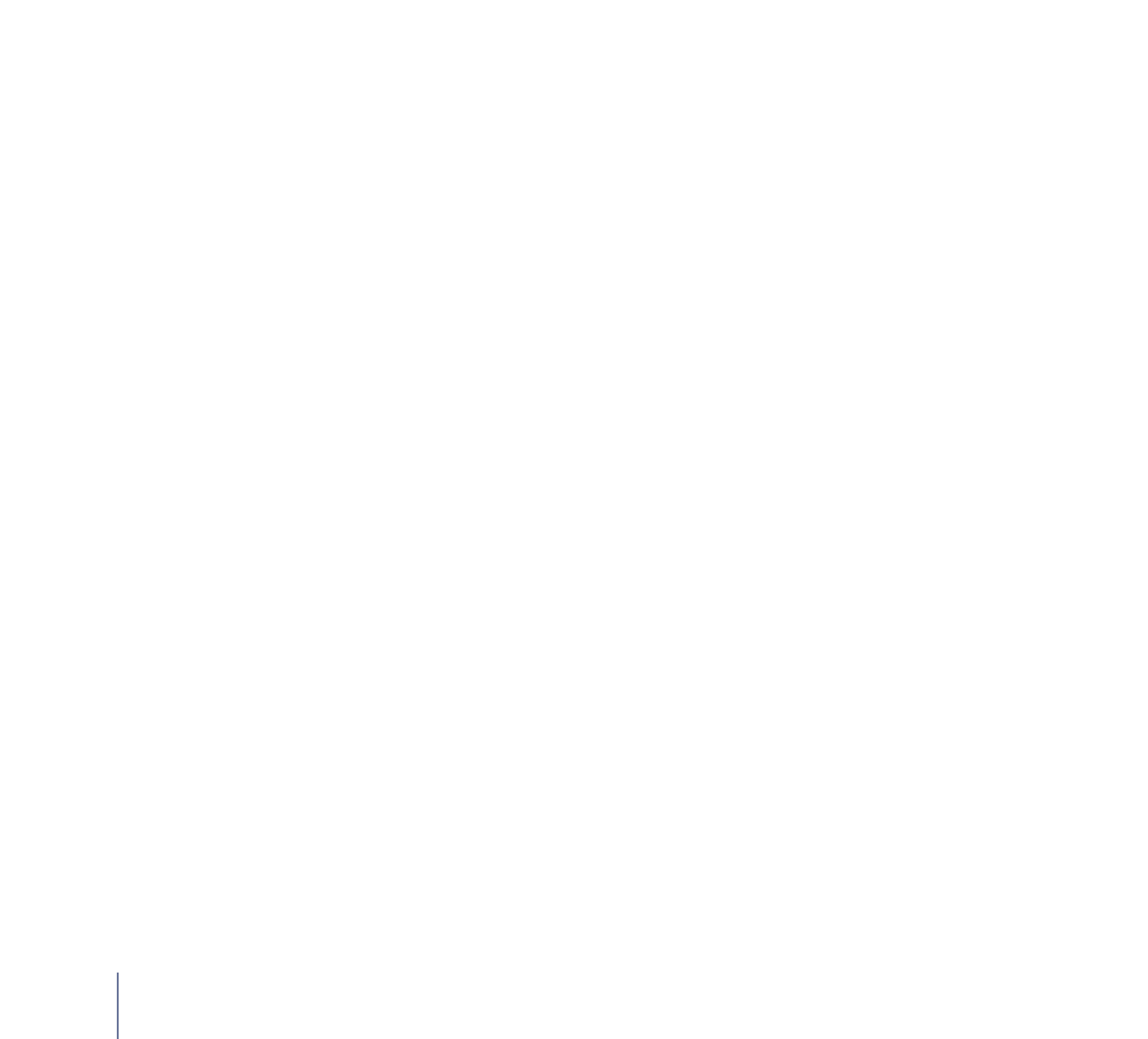
44
ドビュッシー 前奏曲集
を貫いているからです。すべては壊れやすく、過ぎ去るものであり、私たちも、こ
の世の美しさの束の間の証人でしかないのです。
このような認識は、ドビュッシーの音楽語法に何を生み出していると思わ
れますか。
P.B.
ドビュッシーの音楽的な「時間」についての探求の鍵となっていると思いま
す。彼になぜ自由が必要だったか、どんな方法で音楽規範を破ったのか、調性
体系の規則を解放したのか。とは言うものの、彼は調性を頭から投げ出したので
はありません。ドビュッシーの書法は、過ぎ行く時に対する位置づけを表現する
手段だと言えます。伝統的な調性体系(和声規定とそれが形式にもたらす波及
効果のことですが)には、年代的な目印や聴く人にとって「心地よい」指標があっ
て、根を張った感覚や、何かをつかんでいるような感覚が得られますが、ドビュッ
シーの音楽では、これらを完全に失って、人間は、何もできないまま過ぎ去って
ゆく時の中で生きるという条件に直面することになるのです。人間は時間を通り
過ぎるだけの存在になり、無限の中での小さな「挿話」でしかなくなるのです。私
はドビュッシーに、「束の間」という感覚をだんだん強く持つようになっています。
『前奏曲集』をどのように捉えられますか。第一集と第二集の関係についてう
思われますか(
1
)。
P.B.
ふたつの曲集のあいだには大きな違いがあるものの、私にとっては集大
成というべきものです。そこにある違いは、『映像』の第二集が、音の完全な自由
さの追求や並外れた音色の独創性において、第一集よりもずっと先に進んでい
るという違いと同じです。『子供の領分』で一息ついた後、ドビュッシーは『前奏曲

















